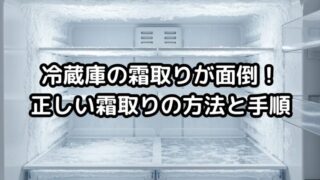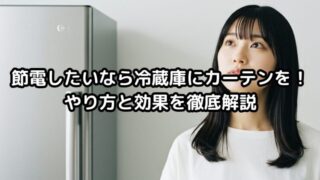1. 冷蔵庫が変える、作り置きのある暮らし
1-1. 作り置きが続かない、そんなあなたに
1-1-1. 平日に作る時間がなくて外食続きに
私も会社勤めをしていたころ、平日の夕方って本当にバタバタで。
仕事が終わって帰ってきたら、もうヘトヘト。そこから料理するなんて無理…ってことで、ついコンビニご飯や外食に頼りがちでした。
でも、それが続くと栄養も偏るし、お財布もどんどん軽くなるんですよね。
「今週も自炊できなかったな〜」って自己嫌悪に陥る週末…。そんなことを何度も繰り返していました。
そこで思いついたのが「作り置き」生活。
ただし、これも簡単ではなくて、最初はうまくいかなかったんです。
1-1-2. 作り置きしたのに食べ忘れて廃棄
最初のころは、気合いを入れて週末におかずを5種類くらい作っていました。
ところが、冷蔵庫の奥にしまったまま存在を忘れて、気づいたときには「期限切れ」…なんてことも。
「あれ、これいつ作ったっけ?」と迷って、結局捨ててしまう罪悪感。
せっかく時間もお金もかけて作ったのに、これじゃ意味がないなと落ち込みました。
原因は単純で、「見える化」ができていなかったんです。
どこに何があるのか、冷蔵庫の中がごちゃごちゃで、自分でも把握できていなかったんですね。
1-1-3. 献立がワンパターンで飽きてしまう
さらに追い打ちをかけたのが、「味に飽きる問題」。
同じレシピをぐるぐる回していたので、3日目あたりで食べたくなくなってくるんですよ。
「またこの味か…」ってテンションも下がって、最終的にはコンビニに走ってしまう、という悪循環。
これでは続かないな、と実感しました。
でも、ちょっとした工夫でこの問題は意外と解決できたんです。
そのヒントは、実は「冷蔵庫の使い方」にあったんですよ。
1-2. なぜ作り置きは三日坊主になるのか?
1-2-1. 保存と管理の知識があいまい
作り置きが続かない理由の一つは、「正しい保存方法」が意外と知られていないこと。
冷蔵と冷凍の使い分けとか、どのくらい日持ちするのかって、なんとなくでやっていませんか?
私も最初は「多分3日くらいは大丈夫だろう」と適当に考えていました。
でも、料理によっては2日が限界のものもあって、知らずに痛ませてしまうこともありました。
1-2-2. 食材が埋もれて存在を忘れてしまう
冷蔵庫が整理されていないと、せっかくの作り置きが「冷蔵庫の奥の住人」に。
見えないと意識からも消えるんですよね。
私も奥にしまったハンバーグを5日後に発見して、泣く泣く捨てた経験があります。
見える化と収納方法って、本当に大事なんだなと痛感しました。
1-2-3. 毎回手間がかかるので続かない
作り置きは「便利そうに見えて、結構面倒」って印象も強いですよね。
まとめて作るのはいいけど、工程が多くて土日がつぶれてしまう感じ。
特に疲れてる週末だと、もうキッチンに立つ気力もない…。
「これって本当にラクになるの?」と疑問を感じて、やめてしまった人も多いかもしれません。
でも、実はちょっとしたコツと冷蔵庫の使い方を工夫するだけで、驚くほどラクになるんです。
次回の本論では、私が実際に試してみて「これは使える!」と感じた冷蔵庫活用法をご紹介しますね。
2. 作り置きを成功させる冷蔵庫活用術
2-1. 作り置き生活のカギは冷蔵庫にあり
2-1-1. メニューは3日分を目安に作るのがコツ
私が作り置きを始めた頃、張り切って1週間分も作っては、後半は食べきれずに捨ててしまう…そんなことがよくありました。
でも、食材の鮮度や味の変化を考えると、作り置きの目安は3日分がちょうどいいんです。冷蔵保存でも安心しておいしく食べられる期間だし、飽きる前に食べきれるのもポイント。
たとえば、週末に3品作っておくと、平日夜は「主菜+ごはん+ちょっとした副菜」で十分満足できるんですよ。無理せず、おいしいうちに食べる。この「ほどよさ」が、作り置き生活を続けるコツだと実感しています。
2-1-2. 透明タッパーで中身を見える化
以前は、色も形もバラバラのタッパーを使っていたのですが、どれに何が入っているのか一目でわからず、結果、食べ忘れ→廃棄の流れに…。
そこで取り入れたのが「透明タッパー」。これ、ほんっとうに便利です。冷蔵庫を開けたとき、パッと中身が見えるので、使い忘れ防止になりますし、「これ、もうすぐ期限かも」ってすぐ気づけるんです。
100均や無印良品、ニトリなどでも手軽に買えるので、見た目をそろえつつ、冷蔵庫内もスッキリ!気分も上がりますよ。
2-1-3. 週末に仕込み→平日は“詰めるだけ”
私は日曜の午前中に買い物&仕込みを済ませるのがルーティンです。カット野菜や茹でたおかずをいくつか作っておけば、平日はフライパンを使わずに済むことも。
「今日は疲れた…でもちゃんと食べたい」っていうとき、詰めるだけのお弁当やお皿に並べるだけの夜ごはんがあると本当に助かります。
週末の1〜2時間が、平日5日間をラクにする。ちょっとの工夫で、毎日がぐっとスムーズになりますよ!
2-2. なぜ作り置きが無駄になってしまうのか
2-2-1. 家庭の冷蔵庫は保存温度が不安定
意外と見落としがちなのが「冷蔵庫の温度管理」。家庭用冷蔵庫は、ドアの開け閉めが頻繁にあるため、庫内の温度が安定しにくいんです。
農林水産省の資料でも、冷蔵庫内の温度は5℃以下が望ましいとされていますが、頻繁に開けていると7℃前後になることも。特に作り置きは、温度が上がると傷みやすくなるので注意が必要です。
私も以前、冷蔵庫の温度設定を強めにしただけで、食材の持ちがよくなったことがありました。温度管理、侮れません。
2-2-2. 奥行きの深さが“見えない食品”を生む
家庭用冷蔵庫って、奥行きが深いものが多いですよね。そのせいで、奥に入れた作り置きが“存在を忘れられる”現象が頻発します。
「これ、いつ作ったんだっけ?」と悩んだ末に捨てる…そんな経験、ありませんか?私もよくやってしまっていました。
対策としては、手前にすぐ使う物、奥には期限の長い調味料などを置く「ゾーン分け」。トレーにまとめるのもオススメです。そうすることで“埋もれる作り置き”がぐっと減ります。
2-2-3. 調理済み食品の消費期限が短い
手作りのおかずは安心安全…と思いきや、意外と日持ちしないんです。特に水分の多い煮物系や和え物は、冷蔵保存でも3日が限界。
消費者庁の資料によると、家庭での調理済み食品は、冷蔵でもなるべく早く食べるよう推奨されています。つまり、「早く食べる前提」で作り置きすることが大前提。
保存期間を意識せず、「あとで食べよう」と放置してしまうと、結局は廃棄に…。自分の食べるペースも把握しながら作り置きするのが大事です。
2-3. 冷蔵庫+工夫で作り置きを成功させる方法
2-3-1. 「作り置きカレンダー」で消費管理
「いつ作ったか」「いつ食べる予定か」が一目でわかるように、私は冷蔵庫に「作り置きカレンダー」を貼っています。
マスキングテープでタッパーに日付を書くだけでもOK。曜日ごとに「このおかずは水曜までに食べる」と決めておくと、ムダが激減!
「ラベリングで食べ忘れがなくなった!」という声、多く見かけます。ちょっとした工夫で管理しやすくなるんです。
2-3-2. 冷蔵・冷凍の併用でフレキシブルに保存
全部を冷蔵するのではなく、一部は冷凍するのも大切なテクニック。たとえばカレーやシチューなど、冷凍しても味が落ちにくいものは、最初から冷凍用と分けておくのがオススメです。
また、冷凍しておけば「今週は食べきれないかも」という時も安心。私はラップで小分けして冷凍→レンジでチンの流れが習慣になっています。
冷蔵と冷凍、上手に使い分けると、作り置き生活がぐっとラクになりますよ。
2-3-3. 省スペース容器で冷蔵庫内を効率化
最後にオススメしたいのが、省スペース容器の活用です。スタッキングできる容器や、仕切り付きの保存容器などを使うと、冷蔵庫内がとってもスッキリ。
無印良品やIKEAの容器、最近ではAmazonで買える日本製のコンパクトタッパーも人気です。「容器の高さをそろえるだけで取り出しやすくなった!」という口コミもよく見かけます。
整理された冷蔵庫は見た目も気持ちも整います。やる気がない日でも「ちょっと頑張ろうかな」って思えたりするから不思議です。
3. 作り置き生活は「冷蔵庫しだい」で変わる
3-1. まとめ:冷蔵庫を整えることで作り置きはもっと続く
3-1-1. 作り置きは「見える・分かる」が重要
作り置きを長く続けるためには、何がどこにあるか分かる収納が欠かせません。私自身、「見えないタッパーはなかったことになる」という失敗を何度も経験してきました。
3-1-2. 冷蔵・冷凍を使い分けてロス削減
「これは冷蔵、あれは冷凍」と保存期間と食事計画をリンクさせる工夫で、食材のロスはぐっと減ります。冷凍ストックがあると、急な予定変更でも安心です。
3-1-3. 習慣化すれば節約と健康の両立が可能
週末に作り置きしておけば、外食が減って食費ダウン&栄養バランスもアップ。ちょっとした手間が、家計と健康の両方に効いてきますよ。
3-2. 使えるおすすめアイテムとリンク集
作り置き生活を支えてくれている、私の愛用品をご紹介します。「これがあると違う!」と実感したアイテムばかりです。
3-2-1. 「冷蔵庫仕切りケース」
100円ショップのSeriaで手に入る仕切りケースは、ジャンルごとに食材を分けて収納するのにピッタリ。野菜、調味料、おかずなどが迷子にならず、冷蔵庫を開けた瞬間にどこに何があるか分かります。
ネットでも「冷蔵庫内が一気に整った!」と口コミ多数。私も朝の時短に大助かりしています。
3-2-2. 「iwaki耐熱ガラス容器」
耐熱ガラスの容器は、冷蔵・冷凍・電子レンジすべてOK。匂いや色移りが少ないのも嬉しいポイントです。
Amazonでレビューを見ても、「作り置き初心者に最適」「そのまま食卓に出してもおしゃれ」と大人気。私も一度使ったらプラスチック容器には戻れなくなりました(笑)。
iwaki(イワキ) 耐熱ガラス 保存容器 クールグレー パック&レンジ 200ml×4 おまけ付き
3-2-3. 【無印良品】の「ポリプロピレン保存容器」
無印の保存容器は、サイズがそろっていて重ねやすく、省スペースで収納しやすいのが魅力。引き出し式の冷蔵庫でも使いやすく、出し入れのストレスが激減しました。
SNSでも「スタッキングできるからごちゃつかない」「見た目がすっきりして気分がいい」と好評。シンプルで長く使える名品です。
無印良品 ポリプロピレン保存容器になるバルブ付弁当箱・白 レクタングラー/約325ml MDC10A8S
3-3. 作り置き生活、まず始める一歩
作り置き生活って、はじめの一歩がちょっと大変。でも、実は意外と簡単なんです。ここからは、すぐに始められるステップをご紹介します。
3-3-1. 週末に「1食×3日分」の作り置きを試す
まずは「主菜1つ×3日分」だけ作ってみてください。ハードルは低めでも、「あ、作り置きって便利かも」ってすぐに実感できるはずです。
たとえば、鶏の照り焼きを3食分。1食はその日の夜に、1食はお弁当に、残り1食は冷凍。これだけでも、平日がぐんとラクになりますよ。
3-3-2. 冷蔵庫を空にして整理→ゾーン分け
スタート前に、一度冷蔵庫をまっさらにするのがおすすめ。中途半端な調味料や期限切れの食品、けっこう眠ってるんです…。
整理後は、作り置きスペース、お弁当用、朝食用などゾーン分けすると、冷蔵庫が“使える冷蔵庫”に早変わり。私は「左から食べる順」と決めて、迷わない仕組みにしました。
3-3-3. スマホのメモアプリで食材管理スタート
最後はデジタルの力も借りること。スマホのメモアプリに、冷蔵庫内の作り置きメニューと日付を記録するだけで、食べ忘れや買いすぎが防げます。
私は「Google Keep」を使って、いつ作って、いつまでに食べるかを書いています。「冷蔵:筑前煮(5/4)」みたいに簡単でOK。買い物中にも確認できて便利ですよ。